1855年まで、日本にはオランダの外交官が駐在していなかった。「カピタン」と呼ばれる商館長が管理する、交易所であるオランダ商館があるだけだった。
この状況が変わったのは、最後のカピタンであるヤン・ヘンドリック・ドンケル・クルティウス(1813年~1879年)が、「駐日オランダ理事官」に任命されたときである。オランダ政府は、ドンケル・クルティウスに外交上の正式な地位を与えたわけではなく、彼の立場がいかにも重要であるように見せるために、肩書を作ったのだ。しかしドンケル・クルティウスが残した功績を見ると、彼がまぎれもなく外交官であったことがわかる。ドンケル・クルティウスは、日本と最初の通商条約の交渉を行い、オランダの外交官として江戸幕府と交流する。
彼の後任にあたるヤン・カーレル・デ・ウィト(1819年~1884年)は、1860年から1863年まで日本に駐在し、総領事に任命される。その後任のディルク・デ・グラーフ・ファン・ポルスブルック(1833年~1916年)も、同じく総領事に任命される。
1868年から1901年まで、日本のオランダ外交官は駐在公使の階級が与えられていた。その後、駐在公使の階級は特命全権公使に格上げになる。1952年、東京のオランダ公使館ははついに大使館となり、大使がその長を務める。
なぜこのような立派な肩書が存在し、それぞれどのように異なるのか。大使、特命全権公使、総領事は実際にどんな仕事をしているのだろう。
1815年のウィーン議定書
15世紀にヨーロッパで駐在外交使節団の制度が始まって以来、外交使節の階級は、国の重要度によって決められていた。そのため外交使節の肩書と地位は、現在のように確立されておらず、ひどく曖昧であった。
ナポレオン戦争による混乱の後、政治的秩序を再構築するために開かれたウィーン会議には、ヨーロッパ諸国の外交官が集まり、外交使節の階級について共通のルールが定められる。ウィーン会議では、外交使節の席次は、階級ごとに任命が正式に通知された日付順に決まると定められ、階級は以下の通り規定された。
- 大使
- 特命全権公使
- 駐在公使(1818年のアーヘン会議で追加された)
- 臨時代理大使
この階級に従い、正式な会議で紹介される順番や、宴会の際の席順、整列時の位置などに関する詳細が決まる。この制度は基本的に現在も同じである。
外交使節団
1961年の外交関係に関するウィーン条約において、外交使節団の役割には以下が含まれると成文化される。1
- 駐在国において、自国を代表する。
- 駐在国において、自国と自国民の権益を守る。
- 駐在国の政府と交渉をする。
- 駐在国の状況やその発展を報告する。
- 自国と駐在国間の友好関係を促進し、経済・文化・科学技術に関する交流関係を発展させる。
- パスポート、渡航文書、ビザの発行など領事業務、および駐在国における自国民の援助を行う。
以下がそれぞれの外交使節階級の説明である。
外交使節階級
使節団を代表する階級
大使 | Ambassador
大使は2国間関係におけるあらゆる面において、使節団の中で最高の席次を有する外交官として自国を代表し、ネットワークを構築、門戸を開く役割を担う。歴史的には、戦争、平和、安全保障に関することが主要な職務であった。後に貿易がより重要な職務となる。現在は職務の幅が広がり、文化交流からイノベーションのための協力までその範囲は多岐に渡る。
大使は昔は珍しい肩書であった。大国、連合国同士、交流のある君主国同士の間でのみ、互いの国に大使を送っていた。「下位」とされた国々には、公使館と公使が存在した。1945年の第2次世界大戦後、国連が全ての独立国の主権平等を宣言すると、公使館と公使は大使館と大使に昇格する。駐日オランダ公使館が大使館になったのは、1952年のことである。2
特命全権公使 | Envoy extraordinary and minister plenipotentiary
公使館の長を務め、通常は「公使」と呼ばれる。1901年以降、オランダ公使館の長はこの階級を与えられていた。「特命全権公使」という肩書は使われていないが、駐日オランダ大使館で現在2番目の席次を有する。肩書は「全権公使」である。
駐在公使 | Minister resident
3番目の席次を有する階級。1968年から1901年まで、駐日オランダ公使館は駐在公使が監督していた。この階級は、1961年の外交関係に関するウィーン条約で廃止となる。
臨時代理大使 | Chargé d’affaires
外交使節団長が不在の期間、あるいは使節団長の交代期間に、その代理を務める人物の肩書。通常は大使の次に高い席次を有する人物が臨時代理大使となる。
その他のスタッフ
参事官 | Counselor
外交使節の上位階級で、現在も使われる肩書。同時に複数の参事官がいる場合がある。20世紀初め、参事官はオランダ公使館の代表顧問であり、オランダ公使館で2番目の席次を有していた。
書記官 | Secretary
書記官とはかつて、事務職員および顧問としての役割を担っていた。今日のオランダ大使館書記官は、政治、貿易、経済、文化などの外交業務を行う立場である。日本についてオランダに報告したり、日本の各省と連絡を取ったりする。オランダの外交使節団には、一等書記官、二等書記官がいる。三等書記官の肩書は廃止された。
書記生 | Chancellor
書記生という肩書は、かつて事務管理職の長を指した。駐日オランダ大使館は、今はもうこの肩書を使っていない。現在、駐日オランダ大使館には、建物、土地、人事、その他関連業務の責任を負う管理・領事部長がいる。
総領事 | Consul general
総領事館の長。総領事館は大使館の下に属する在外公館である。在大阪オランダ総領事館は、西日本の領事、経済、文化に関する責務を負う。
1860年から1868年まで、日本におけるオランダの「外交」使節団は、総領事館であった。当時のオランダ総領事は、政治問題も処理していたため、実質的には公使館だったと言える。デ・グラーフ・ファン・ポルスブルックオランダ総領事は、スイス、ベルギー、デンマーク、スウェーデン、ノルウェーが、日本との間で結んだ通商条約の締結にも協力している。
今日の総領事は政治に関する職務は担わず、条約交渉もしない。現在それは大使館の管轄である。とはいえ、今はオランダ大使もその担当ではない。EU(欧州連合)がその責務を負うからである。
現代的意味での駐日オランダ総領事館は、1930年に神戸に設置されたものが最初である。
領事 | Consul
総領事の下、および副領事の上の階級。「領事」という言葉は、領事館の役人全員を指す言葉としても一般的に使用される。
名誉領事 | Honorary consul
名誉領事は、外交官ではない。多くの場合、任務地の国民が、名誉領事として仕事を行う。オランダの商業的利益を代表し、緊急の際には在外オランダ人を支援する。
執筆者のG・R・ベリッジは『DIPLOMACY: THEORY AND PRACTICE, 6TH ED.』(出版社:PALGRAVE-MACMILLAN)の著者であり、その他にも外交官の仕事に関する本を複数執筆している。
脚注
- 脚注はこのサイトにのみ表示され、書籍には表示されません。
1 Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocols, Article 3, April 18, 1961.
2 Petrus Ephrem Teppema (1890–1960) was the first Dutch ambassador in Japan. Poelgeest, L. van (1999). Japanse besognes. Nederland en Japan 1945-1975. Sdu Uitgevers, 130.
公開:
編集:
引用文献
G・R・ベリッジ()・総領事って何ですか?、出島から東京へ。2025年11月05日参照。(https://www.dejimatokyo.com/articles/21/100-deep-dive-what-is-a-consul-general)
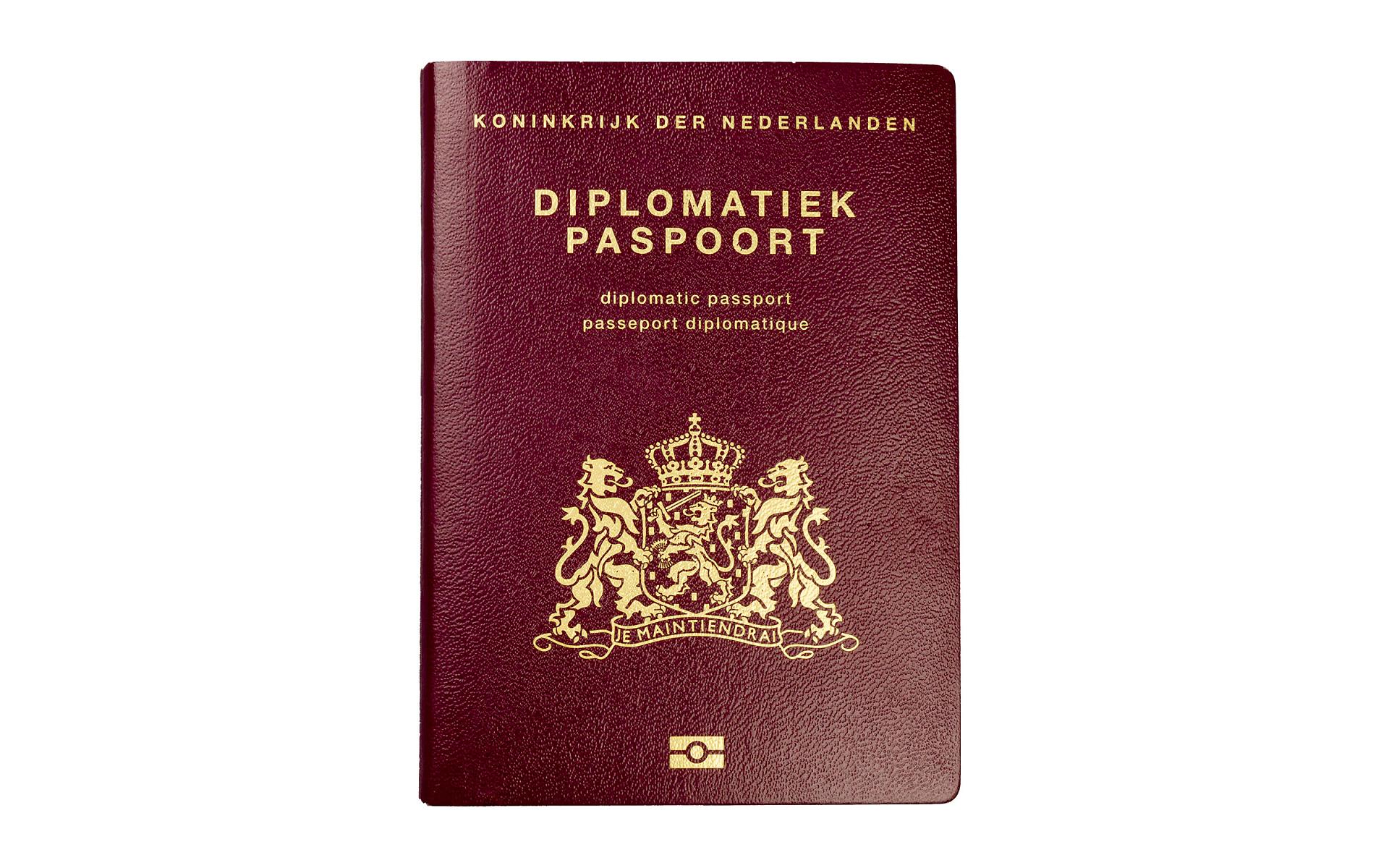

この記事のコメントはまだありません。